企業のビジネス文書やWebサイトなどで「本記事」「当記事」という表現を目にしたことはありませんか?
一見似ているこれらの言葉ですが、適切な場面で使い分けることで、より正確な意図伝達が可能となります。
この記事では「本記事」と「当記事」の違いや適切な使い方をわかりやすく解説します。
「本記事」と「当記事」の違い
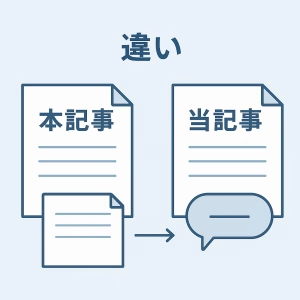
言葉の違いの解説
「本記事」は「自分側」のビュー、つまり編者や書き手が直接記した内容を指す表現です。記事作成者の立場から、責任を持ってまとめた情報であることを強調する際に用いられます。
一方、「当記事」は「読者側」のビューを表します。読み手が現在目にしている記事そのものを指す際に使用され、読者目線で情報にアクセスしてもらう意図が込められています。
| 項目 | 本記事 | 当記事 |
|---|---|---|
| 意味 | 自分が直接記した内容 | 読者が現在読んでいる記事 |
| 視点 | 書き手中心 | 読み手中心 |
| 使用意図 | 自らの責任や公式性を強調 | 読者の現状認識に寄り添う |
使う人の立場と、読まれる環境に応じて、これらの表現を適切に切り替えることが重要です。文章の目的やターゲットに合わせた細やかな言葉選びが、伝わりやすさと信頼性を高めるポイントとなります。
使用する際の注意点
文脈に応じて、「自分が書いたのか」「読者が読んでいるのか」という視点を明確に意識して選択することが重要です。
特に、読者にとって受け取りやすく提供するためには、情報の発信者と受け手の関係性を適切に表現する必要があります。
- 「本記事」を使うべき場面
- 執筆者自身が主体となって解説・報告を行うとき
- 公式性や責任の所在を強調したいとき
- 「当記事」を使うべき場面
- 読者が今まさに読んでいるコンテンツを示したいとき
- 案内やガイドラインとして親しみやすさを重視したいとき
このように視点を意識して言葉を選ぶことで、読者に対して自然で違和感のない印象を与え、文章全体の読みやすさと信頼性を高める効果が期待できます。
ビジネスシーンにおける適切な使い分け
ビジネスの場面では、文章の役割や読者の立場に応じて「本記事」と「当記事」を正しく使い分けることが求められます。
- 招待文や案内文など、読者に直接語りかけるケースでは、現在読者が見ているコンテンツに言及するため「当記事」を使うのが適切です。
- 例:「当記事をご覧ください」
- 一方、研究報告や社内資料のように、編者自身が責任を持ってまとめた情報を示したい場面では「本記事」が適しています。
- 例:「本記事にて調査結果を報告します」
それぞれの用途と読者視点を意識し、適切な表現を選択することで、文章の意図がより明確に伝わり、読み手との信頼関係を築くことができます。
「本記事」と「当記事」の意味と使い方
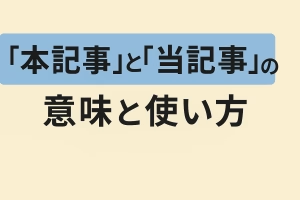
「本記事」と「当記事」の基本的な定義
「本記事」は、編者や書き手の立場から、自分が直接執筆・編集している記事を指す表現です。
責任を持って内容を作成したことを明示する意図が含まれており、ビジネス文書や公式な文書で好んで使用されます。
一方で、「当記事」は、読者が現在閲覧している記事そのものを指します。
執筆者側の立場よりも、読者側の視点を意識した表現であり、案内文や説明書、広く一般向けのWebコンテンツなどで多用されます。
特に、ユーザー目線で親しみやすさや明快さを重視する場面に適しています。
「本記事」の具体的な使い方の例
「本記事では、最新のSEO戦略について解説します」
このように、自分が制作した記事を指し示したい場面で「本記事」が使用されます。
「当記事」を使用する場面
「当記事をご一読頂きありがとうございます」のように、読者に向けたメッセージで使用されます。
また、以下のようなシーンでも積極的に使われます。
- サービス案内やFAQページなど、読者が現在目にしているコンテンツに直結する説明を付けたい場合
- ユーザーガイドや製品サポートページで、読者が読む資料そのものを指し示したい場合
「当記事」を使うことで、読者が今まさに見ている対象への親しみやすい案内が実現できます。発信者の立場を強調せず、読者目線に立った、わかりやすい表現を意識している点が特徴です。
ポイントまとめ
| 項目 | 本記事 | 当記事 |
|---|---|---|
| 指す対象 | 書き手が作成した記事 | 読者が今見ている記事 |
| 主な視点 | 執筆者中心 | 読者中心 |
| 用途 | 公式文書、ビジネス文書 | サービス案内、FAQ、ガイド |
具体的な例文を通じた理解
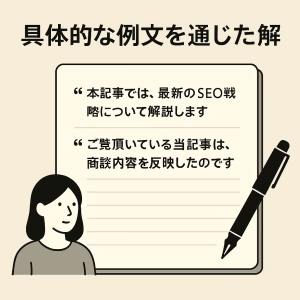
「本記事」を使ったビジネスメールの例
「本記事では、新商品の特徴を解説します」
このような表現は、編者や記者自身が直接説明したい場合に適しています。
「本記事」という表現を使うことで、
-
読者に対して「信頼性のある情報を提供している」という印象を与えることができます。
-
また、ビジネスメールなどでは、たとえ情報量が限定的な場合でも、自分側の立場を明確にすることで、
-
読み手に対する説得力や納得感を高める効果が期待できます。
「当記事」を使用した例
「ご覧頂いている当記事は、商談内容を反映したものであり、説明会やプレゼンテーションで解説した資料とも連携している内容となっています。
このように「当記事」を使用することで、言及者自身の立場を強調するのではなく、読者が現在目にしているコンテンツそのものを直接指し示すニュアンスが生まれます。
「本記事」が「私たちがまとめた」という作者視点を含んでいるのに対して、「当記事」は読者が対象としている現物そのものにフォーカスするため、案内文や商談フォローなどで、読者に寄り添う説明を行いたい場面に適しています。
「本記事」と「当記事」の読み方
正しい発音と読み方
「本記事」は「ほんきじ」と読み、英語表記では “hon-kiji” と表記されます。
「当記事」は「とうきじ」と読み、英語では “tou-kiji” と表記されます。
発音の正しさを意識することは、官方文書やビジネスコミュニケーションなど、フォーマルな場面での言葉の信頼性を高めるためにも非常に重要です。
適切な発音を心がけることで、相手に正確で信頼感のある印象を与えることができます。
読み方の注意点
「本」や「当」の発音は、演説や話し方の癖によって微妙に差異が出ることがあります。そのため、正確な発音に常に注意することが大切です。
特に、会話や発表などの公的な場で、不自然に聞こえる発音をしてしまうと、情報の信頼性を損なうリスクが高まります。
- 正しい発音を心がけることで、聞き手に安心感を与えられます。
- ビジネスや公式の場面では特に発音ミスに注意しましょう。
演説による次第的な発音変化を防ぐためにも、日頃から意識して正しい読み方を練習することが重要です。
英語での表現
英語で「本記事」は “This article”、 「当記事」は “the article” と表現されます。
- This article:自分が立場を明確にしながら描いた記事を指します。
- the article:読者が現在読んでいる記事を示すニュアンスを持ちます。
このように、日本語だけでなく英語でも「本」と「当」の意識の差を伝えることができるため、文脈に合わせて適切に使い分けることが重要です。
「本」・「当」に関するFAQ
よくある質問とその回答
Q. 「本記事」と「当記事」を入れ替えても問題はありませんか?
A. 大きな文脈の第一段階ではおおむね互換性がありますが、表現の精度を重視する場面では適切な使い分けが求められます。
- 本記事:執筆者側の立場を強調し、「私たちがまとめた情報」というニュアンスを持ちます。
- 当記事:読者が目にしているコンテンツそのものにフォーカスを当てた表現です。
そのため、ビジネス文書や公式案内など、発信側の意図や信頼性を強調したい場合は「本記事」を、 読み手に寄り添った案内や補足を行いたい場合は「当記事」を使用することで、より的確なコミュニケーションが実現できます。
「本記事」「当記事」の関連用語について
「本問題」「当問題」といった表現も同様に使い分けがなされます。
- 発信側の立場を強調したい場合:本問題
- 読者側に近い立場で示したい場合:当問題
その他にも、「本サイト」と「当サイト」のように、場面や文脈に応じた適切な使い分けが求められる例が多く存在します。
使用が推奨される場面とその理由
公式文書や証明文書、企業の公式発表、およびそれに付随するプレスリリース文書などでは、特に「本」の使用が推奨されます。
これは、
- 発信側の立場を明確に示し
- 文書の公式性や信頼性を高める
といった効果を狙うためです。
また、外部だけでなく社内向け文書においても、受け取る側に不自然な印象を与えず、正当性を確保しやすくなるという理由から、 「本」表現の使用が適しているとされています。
まとめ:正しい使い方を理解しよう
重要なポイントの再確認
「本記事」は、自分側、つまり執筆者や発信者の立場から記述した内容を指します。
一方、「当記事」は、読者側、すなわち閲覧者が現在目にしている対象を指す表現です。
この違いをしっかり理解した上で、文脈に応じた適切な使い分けを行うことが大切です。
特に、ビジネス文書や公式案内などでは、発信意図を正確に伝えるために、両者を意識的に選択する必要があります。
- 本記事:発信者の立場を明確にし、公式性や信頼性を高めたい場合に使用。
- 当記事:読者に寄り添い、案内や補足に自然な流れを作りたい場合に使用。
正しい使い分けを心がけることで、文章の信頼性と読者の理解度を高めることができるでしょう。
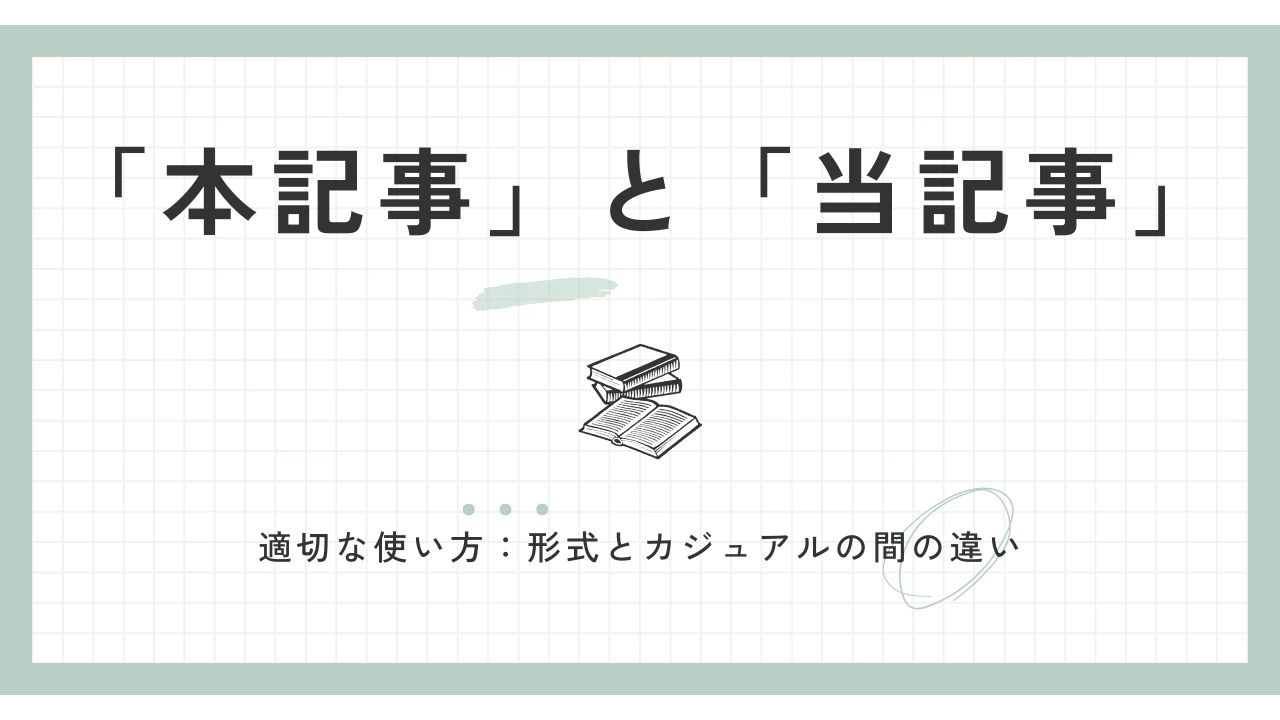
-120x68.avif)
