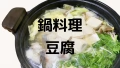日本の伝統行事や四季の移ろいを深く味わううえで欠かせないのが旧暦月名。
しかし「睦月・如月……師走」まで一気に覚えるのは意外と大変です。
この記事では、旧暦月覚え方のコツをまとめ、だれでも楽しく・効率的にマスターできる方法を紹介します。
加えて、学んだ月名を暮らしや趣味にどう活かすかまで具体例を広げました。
旧暦月覚え方|はじめに〜楽しく覚えるためのポイント〜
旧暦とは?現代の暦との違いと月名の歴史的背景
- 太陰太陽暦に基づく旧暦は、月の満ち欠けを基準にした日本伝統のカレンダー。
- 明治6年(1873年)に新暦(グレゴリオ暦)へ移行した後も、七夕・お盆・十五夜など多くの行事で旧暦が生き続けている。
- 各月名は自然現象や農作業と結び付いており、古来の暮らしぶりを映し出す“言葉のタイムカプセル”。
- 旧暦は約354日で一年が短いため、3年に1回ほど閏月(うるうづき)を設けて季節のズレを調整するしくみも魅力的。
- 月名は奈良~平安期にかけて徐々に定着し、宮中行事や和歌・俳諧の季語として用いられながら庶民に普及していった。
旧暦月名の覚え方を知るメリットと活用シーン
- 行事を深く理解:旧暦ベースの祭りを“日付感覚ごと”味わえる。
- 語彙力アップ:和風表現・季語を自然にインプット。
- 子どもの学習支援:歴史・国語・理科(天体)の横断学習に最適。
- 趣味・SNS発信:季節の投稿や俳句、茶道の席で重宝。
- ビジネス文書で差別化:季節の挨拶やニュースレターに月名を添え、文章に風情をプラス。
- 訪日観光ガイド:外国人に日本文化を説明する際の話題作りに役立つ。
旧暦月名(1月から12月まで)の一覧と由来・意味
の一覧-500x345.webp)
旧暦一覧表|1月から12月までの月名・和風名・異称まとめ
| 新暦目安 | 旧暦月名 | 読み | 主な由来・キーワード | 関連行事・風物詩 |
|---|---|---|---|---|
| 1月下旬〜2月 | 睦月 | むつき | 親族が睦み合う正月 | 初詣・おせち・七草粥 |
| 2月下旬〜3月 | 如月 | きさらぎ | 衣を重ねる衣更着 | 節分・梅見・針供養 |
| 3月下旬〜4月 | 弥生 | やよい | 草木が弥(いよいよ)生い茂る | ひな祭り・春分・花見 |
| 4月下旬〜5月 | 卯月 | うづき | 卯の花が咲く季節 | 八十八夜・種まき・花まつり |
| 5月下旬〜6月 | 皐月 | さつき | 早苗を植える田植え月 | 端午の節句・田植え祭 |
| 6月下旬〜7月 | 水無月 | みなづき | 田に張る水の月/梅雨明け | 夏越の祓・水無月和菓子 |
| 7月下旬〜8月 | 文月 | ふみづき | 七夕の文(短冊) | 七夕・土用の丑・祇園祭 |
| 8月下旬〜9月 | 葉月 | はづき | 木の葉が色づき始める頃 | お盆・五山送り火・ねぶた祭 |
| 9月下旬〜10月 | 長月 | ながつき | 夜長月、月見の季節 | 中秋の名月・重陽の節句 |
| 10月下旬〜11月 | 神無月 | かんなづき | 神々が出雲に集う月 | 神在祭・秋祭・収穫祭 |
| 11月下旬〜12月 | 霜月 | しもつき | 霜が降り始める | 七五三・新嘗祭・紅葉狩り |
| 12月下旬〜1月 | 師走 | しわす | 僧(師)が忙しく走る年の瀬 | 大掃除・冬至・除夜の鐘 |
ポイント:旧暦は月の“引力リズム”に合わせて動くため、農業・漁業・潮汐観測など自然と共生する場面で今も活用されています。
各月名の由来と意味をより詳しく解説
- 睦月:正月に家族が集い“睦む”月。おせちや初詣で絆を深める時季。元旦に若水を汲み、無病息災を願う神事も。
- 如月:寒さ極まる頃。衣を重ねる=衣更着が語源。梅の蕾がふくらむ早春。「生更木(きさらぎ)」説もあり、草木が芽吹く意味を持つとされる。
- 弥生:桜・菜の花が咲き、命が“いやおい”成長。卒業・入学など節目も多い。古代には”木草弥や生ひ月”と表記された記録も。
- 卯月:卯の花(ウツギ)の白が里山を彩り、農家は種まき本格化。陰暦4月は田楽・花祭りで五穀豊穣を祈願。
- 皐月:早苗月の略。田植えや端午の節句が象徴。菖蒲湯で邪気払いし、吹き流しや鯉のぼりが初夏の風に泳ぐ。
- 水無月:“水の月”が本来の意味。夏越の祓で茅の輪をくぐり、半年間の厄をリセット。京都の氷室祭では氷を献上した歴史も。
- 文月:短冊に願いを書く文披月。暑気払いに土用の丑も。書道・和歌・読書にちなみ「書読(ふみよみ)月」とも。
- 葉月:立秋を迎え、落葉・台風シーズン。五山送り火や盆踊りもこの頃。稲の穂が色づき出す「稲見月」の別称も美しい。
- 長月:夜長・虫の音・名月。稲刈りや重陽の節句で実りに感謝。「稲熟月」や「寝覚月」など別名も多彩。
- 神無月:全国の神が出雲に赴く神議の月。各地では留守神を祀る収穫祭。「雷無月(かみなしづき)」の古称も。
- 霜月:霜降りて紅葉ピーク。七五三で子どもの成長を祝う。冬支度が本格化し、薪割りや味噌仕込みが始まる地域も。
- 師走:大掃除・餅つき・年越しそば。除夜の鐘を合図に新年へ。「年果つ(としかつ)」が転じた語源説や、師=僧侶説など由来は複数。
旧暦月名と季節感の関係〜なぜ現代とズレがある?〜
- 旧暦は新月を1日とするため、月初が毎年変動。月末は必ず朔望月29日または30日で終わる。
- 1年が約354日→3年に1度ほど閏月を追加して季節を補正。閏月にもすべて月名があり「閏皐月」「閏文月」などと呼ぶ。
- 地域によっては今も旧暦行事(旧盆・十六夜祭・沖縄の三月清明)を旧暦日に合わせて実施。
- 中国の節気「二十四節気」や「雑節」と組み合わせると、農業・漁業・漢方の暦生活がより立体的に理解できる。
旧暦月名を簡単に覚える!おすすめの覚え方
旧暦月覚え方歌が効果的!
例:童謡「どんぐりころころ」替え歌
むつき きさらぎ やよい〜♪ うづき さつき みなづき〜♪ ふみづき はづき ながつき〜♪ かんなづき しもつき しわす♪
- メロディにのせることで“リズム記憶”が働き、短期→長期記憶へスムーズに移行。
- 親子・クラス活動にも◎。運動会の隊形移動やリトミックとも相性抜群。
語呂合わせや頭文字で覚える方法
- 頭文字一括法:
むきやう さみふ はなか しし(スペースで4・4・4区切り)。- 4音ずつ刻むとラップ調で唱えやすい。
- 語呂合わせ例:
- 「むし(睦)ろ きさらぎ(如月)で やよい(弥生)の うれしい さくら、 みず(水無月) ふかまる夏、 はる葉月(葉月)の ながい(長月)夜、 かんの(神無月) しくも霜の しわすよ(師走)」
- 多少強引でもOK。映像イメージが湧けば勝ち。
旧暦月名の覚え方アイデア集|イメージやストーリー化で記憶に残す
- マインドマップ:中心に旧暦、枝に月名+風物詩イラスト。色を季節で変えると視認性UP。
- フラッシュカード:表に月名、裏に行事・写真。スキマ時間に反復。
- ストーリーテリング:十二支の動物が12の町を旅する物語など、キャラ設定で没入。
- カルタ遊び:月名札と行事札をマッチング。家族や友人と楽しみながら暗記。
- 語呂ルーレット:円形カードを回して出た月名を即興で説明→アウトプット強化。
- デジタルアプリ:通知で“今日は旧暦◯月◯日”が届くアプリを利用し、日常に刷り込む。
まとめ・旧暦月名を楽しく覚えて暮らしに活かそう
旧暦月覚え方のコツを振り返る
- リズム・歌で耳から覚える → “口ずさめる”と忘れにくい。
- 語呂合わせ・頭文字で簡潔に → テスト前の時短暗記にも。
- 視覚化(表・マップ・カード)で脳に定着 → 色・絵を交えると効果倍増。
- 行事・料理とリンクさせて体験学習 → 五感で感じると記憶は長持ち。
- デジタル+アナログ併用で“ながら学習” → 継続こそ王道。
旧暦月名は、覚えた先に活かすシーンが豊富。俳句や手紙、SNS投稿に添えれば季節感が一気にアップします。ビジネスメールの冒頭や海外ゲストへのおもてなしトークでも大きな武器に。ぜひ自分に合った旧暦月覚え方を試し、日本ならではの暦文化を日常に取り入れてみてください。